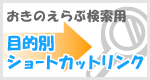沖永良部島ってどんな島なんだろう?
沖縄?奄美?鹿児島?
沖永良部島っていったいどんなところだかわかるかな?
よく「沖永良部って沖縄だよね?」「奄美大島だっけ?」「鹿児島の屋久島の近くだったよね?」って言われちゃうんだけど、
みんなはどこにあるのかわかるかな?
結構知らない人だらけみたいだから、ここでは沖永良部島はどんな島なのか簡単に説明するよ! この島について知りたい人はぜひ見てってね!
沖永良部島の"Q&A"
-
沖永良部島はどこにあるの?
沖永良部島はどこにあるのか教えるよ。
沖縄にあるのか、鹿児島にあるのか、果たしてどっちでしょう??
※ なお沖永良部島への詳しいアクセス方法はこちらをご覧ください。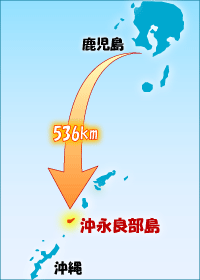
ちなみに鹿児島から沖永良部島に行く場合、飛行機だと約1時間半、船だと約18時間かかります。
沖縄からだと、飛行機で約1時間、船だと約7時間(那覇港)、または5時間(本部港)かかります。
交通の便はあまり良いとは言えないでしょう。
飛行機、船ともに台風などの天候状態にも左右される事があり、事前に天気を確認しておいた方がいいでしょう。
「めんしょり沖永良部島」ではページの左のほうに、奄美地方で天気を表示しておりますが、沖縄北部の天気を参考にしてかまいません。
(沖縄と奄美の中間にあるので、両方を見て予測を立てるのが賢い方法かもしれません。) - どんな島なの?
沖永良部島はどういう島なのか紹介するよ。
この島の生まれた簡単な経緯などの特徴や、島の人口とか大きさとかはいったいどれぐらいなのかな??- 人口
沖永良部には和泊町と知名町という2つの町があり、2つの町を合わせて約1万5千人です。
下記の図のように、左側(西側)が知名町、右側(東側)が和泊町です。 - 大きさ
島の周囲は約60kmあり、歩こうと思えば(歩きっぱなしの場合)日中の間にで一周することもできます。
他の島々より平坦な島と言われてはいますが、それなりに起伏はありますので、観光の場合には休憩をまじえて3日ぐらいで周るといいでしょう。

- 集落
島には2つの町がありますが、それぞれいくつかの集落によって構成されています。
詳しくは下記ページよりご覧ください。
 沖永良部島:地域マップ
沖永良部島:地域マップ
- 特徴
-
性質
もともとは珊瑚礁が隆起してできた島だと言われています(40万年もの時間をかけて今の沖永良部ができたといわれています)。
それ故に、奄美や徳之島、沖縄地方などに生息しているハブは沖永良部島にはいません。島の周りには、珊瑚によってリーフ状に囲まれていて、島自体の性質も石灰質になっています。
また、現在も隆起を続けているので、砂浜自体はいくつかありますが、ほかの島のような規模の大きな砂浜はありません。 -
島の山
この島には越山(こしやま)と大山(おおやま)という2つの山があります。
大山という山の方がが高いのですが、それでも標高246m程度なので、全体的に緩やかな島になっています。 -
鍾乳洞
沖永良部島は島の地下にはいたるところに鍾乳洞があります。
大小さまざまですが、合わせると島全体に鍾乳洞が張りめぐっていて、「鍾乳洞の島」と言われることもあります。それ故に、大学や地形の研究者たちが調査に訪れることもありますが、近年の調査では全長が10kmにもおよぶことが判り、現時点では国内で2番目の大きさをも誇っています。また、一般に公開されている鍾乳洞である「昇竜洞」も規模は大きいいもので、太古から時間をかけて生み出されてきた大自然の造形美を実感することができます。
-
- 人口
- 特産物は?
沖永良部の代表的な特産物を紹介するね。
南国らしい物や、沖永良部島らしい物がいろいろあるから、島に遊びにきたらお土産にもいいかもね ! 沖永良部島の特産物は、沖縄に似たものと沖永良部島独自のものが存在します。
沖永良部島の特産物は、沖縄に似たものと沖永良部島独自のものが存在します。まず代表的なものが、さとうきびです。
これを原料に黒砂糖が作られたり、黒砂糖を使ったさまざまなものが作られています。
豆と黒砂糖をまぜて炒った“ヤジ豆”や、島のドーナッツとも言われている“サーターアンダギー”など、いろいろなお菓子などがありますが、黒糖焼酎なども作られていておススメです。 「はなとり」や「昇竜」といった銘柄がありますが、とても口当たりがよく女性にも飲みやすい方なんじゃないでしょうか。沖永良部島で作られている黒糖焼酎について詳しくはこちらでも紹介していますので、参考にしてください。
 ぬでぃあしば!黒糖焼酎
ぬでぃあしば!黒糖焼酎また、この島は花の種類が多く、花の島ともいわれます。
 主なものとしては、えらぶゆり(テッポウユリ)やフリージア、グラジオラスなどを栽培しています。
春先になると、えらぶゆりの白とフリージアの黄色で畑がうめつくされていてとてもきれいです。
主なものとしては、えらぶゆり(テッポウユリ)やフリージア、グラジオラスなどを栽培しています。
春先になると、えらぶゆりの白とフリージアの黄色で畑がうめつくされていてとてもきれいです。
沖永良部島のマスコットキャラクターであるリリーも白百合の花をモチーフにしたキャラクターです。また、暖かい気候なので年中を通してハイビスカスや菜の花など、いろいろな花が自然に咲いているので心が和みます。
- 食べ物は?
沖永良部島の食物はどんなものがあるかを紹介するよ。
他にも島のご飯を食べられるところをいくつか教えるよ!沖縄に近いこともあり食文化も沖縄と似ています。島にある野菜なども一緒なので、ゴーヤやヘチマ料理や、豚肉を使った料理などは一般的な家庭料理です。
また、魚介類も南国独特なカラフルな魚が多く、島のスーパーなどの魚売り場では、都会では見られないような配色が見られます。 他に果物ではマンゴーやパパイヤ、シークリブ(島みかん)、モンキーバナナなどがあります。
他に果物ではマンゴーやパパイヤ、シークリブ(島みかん)、モンキーバナナなどがあります。
特にパパイヤやシークリブ、バナナなどは農家の方々が畑の片隅で自家製で育てたりしていますが、カラスなどに食べられることがあるので、日々、気をつけています。また、自然になっている物もありますので、沖永良部島に来たときは、ぜひそういった自然にあるものを食べてみるのも良いかもしれません。
次に、島での食事処を紹介したいと思います。

 和泊のほうに「MEIKUMA」というオーシャンビューのお店があり、軽くくつろぎたい場合にはオススメです。島の若者がよく足を運んでいて、ほとんどの若者は行った事がある喫茶店です。
和泊のほうに「MEIKUMA」というオーシャンビューのお店があり、軽くくつろぎたい場合にはオススメです。島の若者がよく足を運んでいて、ほとんどの若者は行った事がある喫茶店です。創作料理の場合は「とうぐら」という食事処があります。こちらも和泊にありますが、魚介類や野菜など島の幸をふんだんにつかった料理が充実しており、満足いくところだと思います。
- 島のイベント・行事は?
沖永良部島で今月行われる行事を紹介するよ!
和泊町、知名町それぞれの行事予定一覧表だよ。 - どんな文化なの?
沖永良部島の文化と歴史を紹介するよ。
詳しく調べれば日本史よりおもしろい!?沖永良部島は、もともと琉球王朝時代にその王国の一部だったことから文化や方言などは沖縄と似ている部分がたくさんあります。
ちなみにこのホームページのタイトルになっている「めんしょり」という言葉は、“ようこそ”という意味で、
沖縄では「めんそーれ」といいます。
方言は若干違いますが、似ているので年配の人はそれぞれの方言を理解できたりもします。歴史としては、琉球の文化を引き継いではいますが、薩摩藩に占領されたり、明治には西郷隆盛が島流しにされた際には沖永良部ですごしていたりと、 琉球文化と多少の大和文化、そして奄美の文化、それぞれの文化が入り混ざっていて、ある意味独特な島であるといえます。
三線を使っての島歌などを、歌ったり踊ったりすることが好きな人も多いです。
(島歌は奄美流ではなく、沖縄のものに近いと言われています。)そして何より愛郷心の強い人たちばかりです。
島ならではの歴史や伝説も多々あるので調べてみても面白いと思います。
(※かつて島を治めていた「世之主(よのぬし)」という人物とその部下達に関する伝説は多々あり、とても面白いと思います。)
こちらでは世之主にまつわる伝説を紹介しています。*下記には沖永良部島の歩んできた歴史のおおまかな年表を載せてあります。
興味のある人は参考にしてください。沖永良部島:年表 ■1266年 琉球の北山王朝に属す。
※琉球王朝ができる前までは沖縄は、北山王朝、南山王朝、中山王朝にわかれていました。■1609年 薩摩藩の侵攻により薩摩の直轄領となる。この時、薩摩藩にサトウキビの栽培を命じられる。
※直轄領時代は、極刑の流刑地とされる。西郷隆盛が島流しで1年7ヶ月滞在した島でもある。■1871年 廃藩置県により鹿児島県となる。 ■1908年 和泊村と知名村が成立(現在の和泊町と知名町)。 ■1946年 第2次世界大戦の敗戦により周辺の奄美諸島と共にアメリカの軍政下に入る。 ■1953年 日本国に返還される。
※この時は、沖縄はまだアメリカ領。■1977年 台風9号(沖永良部台風)が直撃。日本の陸上における最低気圧907.3ヘクトパスカルを記録した。
※降水量は179mm、最大瞬間風速は60.4m/sを記録(観測機が壊れたため、約80m/sまで達したといわれている)、
被害は全住宅の75%まで達し、奇跡的に死者は1人 。
※台風が直撃した4日後の13日に気象庁より「沖永良部台風」と命名されました。
これ以降に名称をつけられた台風はありません。
※この台風9号は、9月9日に沖永良部島を直撃、最低気圧は905 hPa、発生期間は9日間と、
9という数字が並んでいて奇妙な感じでもあります。 - 沖永良部島のかつての統治者、「世之主(よのぬし)」の伝説
沖永良部島を治めていた世之主にまつわる伝説です。
その波乱にみちた生涯はとても悲しい物語だと言われています。世之主の母
時は室町時代である13世紀の後半、沖永良部島のニシミという地区(島の北西部)に美しい娘がいました。
娘の伯母が神女(ノロ)を勤めており、ある時、琉球の北山王国へ上納物を納めに行くことになりました。この時、姪である娘もいっしょに同行する事になります。そして上納の際に、その美しさから国王の目に留まった娘は、城で暮すこととなります。そして城での生活が数ヵ月ほど過ぎる頃、娘はそのお腹に小さな命を授かりました。娘は故郷である沖永良部島に帰ってお産することにしました。
娘は海を渡り、島の上陸しやすい湊に着きましたが、この時、島ではシニグ祭という祭りを行なっており、不浄の女は入れることができないという事で上陸を断念せざるをえません。仕方なく、島の周りを迂回して現在の沖泊という湊に上陸します。ここはニシミにはとても近い湊ですが、高い崖や急斜面がつづき、身重の娘にとって、登るのにはたいへん難儀を余儀なくされます。それでもようやく、懐かしの我が家に辿り着く事ができました。
安心したのもつかの間、父親は娘が不貞を犯したとして、家への立ち入りを許してはくれませんでした。
しかし、自身に授かった命をこの世に誕生させたい娘は、雨の降る中、みずから小さな小屋を作ります。そして娘は無事に男の子を出産しました。
そのときに産湯を沸かし、お粥を炊いたといわれている竈石は、今でも神石として祭られています。成長していく男の子
産まれた男の子は真松千代(ままちちよ)と名づけられ、すくすくとたくましく育ち、父の姿を知らぬまま7年の月日が経ちます。
しかし父の事が気になる年頃でもあります。ある時、母親から出生のいわれを聞き出した真松千代は琉球に渡り、父親である北山王国の王に面会します。しかし王は本当に我が子なのかと疑いの眼差しをむけます。そこで、水鏡の裁きが行なわれることになりました。水鏡の裁きとは井戸の水面に写る顔に王冠がかぶっているかどうかを見て、真実を判定するという裁きです。
井戸を3回廻った真松千代の頭には、見事に王冠がうつし出されていました。
こうして王の子として認められたものの、王は嫡子との争いを恐れ「17歳になったら再登城せよ」と伝えて沖永良部島に帰します。そして17歳になった真松千代は再登城し、生まれ育った沖永良部島を与えられ、島の主である世之主の地位を授けられました。
島を治める世之主
世之主は15世紀の初めに、家臣の一人である後蘭 孫八〔平 孫八〕に築城を命じ、約3年かけて城を築きました。この城跡が現在の「世之主神社」となっていおり、当時の刀などがまつられています。
そして琉球の中山王の娘を嫁にもらい、女の子と男の子を授かります。また、世之主には四天王といわれる4人の家臣がおり、前述した「後蘭 孫八」をはじめ、「屋者 真三郎」、「西目 国内丘衛佐」、「国頭 弥太郎」といったつわものに補佐をされ、善政を行ったとされています。
この四天王にもそれぞれ、多くの伝説が残っていますが、ここでは割愛させていただきますのでご了承ください(後蘭 孫八〔平 孫八〕は平将門の子孫にあたるとされる 等)。均衡が崩れる琉球
この頃の琉球は、世之主の父である北山王が治める「北山王国」、妻の父親が治める「中山王国」、そして沖縄南部に位置する「南山王国」の3つの国から成り立っていました。
3国は争っており、1416年には北山王国は中山王国によって滅ぼされます(1429年に中山王国は南山王国をも滅ぼし、琉球王国を築きあげます)。
そして北山の領地であり、世之主が治めている沖永良部島にも目は向けられます。世之主の悲しき最期
しかし中山王は、自分の娘が嫁いでいる沖永良部には和解の親善使を送ります。
父親の北山王国が滅ぼされたことで、世の主は小さな島の行く末を案じている頃に、多数の船がやってきました。世之主はつわものである四天王に命じ、中山からの船へと向かわせます。四天王には「争いなら赤旗」を、「親善なら白旗」を振るように指示をし、城から監視することにしました。
ところが緊迫する四天王は、親善大使たちからの思いがけない歓待を受け、浜で宴をひらき酒に酔ってしまうのです。そしてあろう事か、赤旗を振ってしまうのです。
それを受けた城内は一大事です。世之主はこの船が沖永良部を攻め取りに来た軍船だと勘違いしました。そして大国にかなわずと、島の人々を救うために自害をしてしまうのです。
早まった判断だったとはいえ、島の人々を救うために自害することを選んだ世之主を、島の人々は手厚く手厚く葬ったのです。
そして、それから約600年たった現在でも島の守り神として、世之主は島の人々から尊敬され世之主神社に祭られているのです。
注:この世之主に関する記述は、沖永良部の民俗学を研究しておられる、かつての恩師、先田 光演 氏から学んだことを中心に、管理人が個人的にまとめた物になります。事実に即した内容を心がけておりますが、解釈の違いにより事実と異なる点がある可能性がありますことをご了承ください。
- この島に行くには?(アクセスマップのページへ) 沖永良部島に行くための交通手段を説明しているよ。
- 島の名所は?(ガイドマップのページへ)
沖永良部島の代表的な観光ポイントを教えるね!
全部行ったことがあれば、君は沖永良部マスター!? - どこに泊まるの?(宿泊施設のページへ) 沖永良部島に来たときに泊まれる宿泊施設を紹介しているよ。
- 島にはどんな集落があるの?地図が見たい!(ダウンロード地域マップのページへ)
島のにある集落を地図で紹介しているよ!
また、ここから島の地図もダウンロードできるから、印刷して使ってね! - 島での移動手段は?(沖永良部の交通機関のページへ) 沖永良部島のレンタカーやタクシーなど、島に着いてからの移動手段を紹介しているよ。